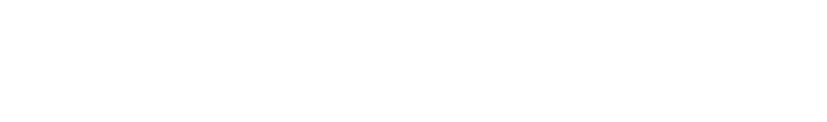講師:倉敷昭久氏(行政書士法人ORCA 代表行政書士)
今日は、私が長年向き合ってきた「相続」と「遺言書」について、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。
「うちは財産がないから大丈夫」
「子どもたちは仲がいいから心配ない」
そんな言葉をよく耳にします。ですが、私はこうお話ししています。本当に争いが起きやすいのは、むしろ財産の少ないご家庭です。なぜ遺言書が必要なのか?遺言書は“特別な人”のものと思われがちですが、実はほとんどの人に必要なものです。むしろ「遺言書が必要ない人の方が少ない」と言っても過言ではありません。
こんな人は特に要注意
- 子どもが複数いて、財産をどう分けるか決めていない
- 再婚して前婚の子どもがいる
- 子どもがいない(相続人が兄弟や甥・姪になる)
- 特定の子どもに多く遺したい/遺したくない
- 生前に援助をしてくれた人に感謝の気持ちを伝えたい
遺言書は、家族への“最後のプレゼント”なんです。特に、配偶者が残される場合には、生活が困らないようにという想いを込めて、きちんと用意しておく必要があります。
相続トラブルの現実
・遺産分割をめぐる裁判件数は、毎年右肩上がり。
・裁判所に持ち込まれているのは年間15,000件以上。(実際にはその10倍以上がもめごとになっている可能性があるとのことです。)
資産1,000万円以下でも、争いは起こります。「相続税がかからない=トラブルもない」ではありません。
遺言書の正しい書き方
遺言書は「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」が主流ですが、それぞれにメリット・デメリットがあります。
| 種類 | メリット | 注意点・リスク |
| 自筆証書遺言 | 手軽、費用なし、いつでも書ける | 無効になる例が多い、発見されにくい |
| 公正証書遺言 | 法的に強い、無効の可能性が少ない | 費用・証人が必要 |
私は数千件の遺言書を作ってきましたが、公正証書遺言をお勧めしています。無効になる遺言書を何枚も見てきたからです。
実際によくある失敗例
- 「妻に全財産を相続させる」と書いたが、実は内縁関係だった
- 財産の一部しか書かず、残りでトラブルに
- 「みんなで仲良く分けてね」と締めくくって意思が不明確に
笑い話のようですが、現実に“これ使えませんね”という遺言書が持ち込まれることは非常に多いです。
遺言書でできること
- 法定相続人以外にも財産を渡せる
- 相続分を自分で自由に決められる
- 相続争いを防ぐ
さらに、遺言執行者を指定しておけば、高齢の配偶者が手続きを進められない場合でもスムーズに遺産整理ができます。
まとめ
- 遺言書は「財産のある人」だけのものではない
- 書き方ひとつで、家族の未来は変わる
- まずは「誰に、何を、どれだけ」を書くところから
最後に倉敷先生からのメッセージ
遺言書は、自分の“思い”をカタチにするものです。誰に何をどれだけ渡すか、明確にしておくこと。それが、家族を守る一番の方法だと思います。まずは、一度書いてみてください。書いた遺言書は、専門家に見せていただければ、チェックします。ぜひ、あなたも今日から始めてみてください。
[講師プロフィール/倉敷昭久氏]
1959年鳥取県米子市生まれ。行政書士法人ORCA 代表行政書士。神奈川大学経済学部卒業。米子市役所臨時職員等を経て、2003年に43歳で行政書士試験に合格。同年、米子市に行政書士倉敷昭久事務所(個人事務所)を開設し、相続専門事務所として業務を開始する。2010年に行政書士法人となり、2022年に行政書士法人ORCAに法人名称を変更。現在、鳥取(本社)、東京、神奈川、北海道、山形、新潟、石川、愛知、三重、大阪、兵庫、岡山、香川、広島、島根、山口、沖縄にオフィスを構え、全国47都道府県で活動中。年間相談件数14,000件(グループ計)を超える、日本一の相続専門行政書士法人を経営している。
[参考図書]
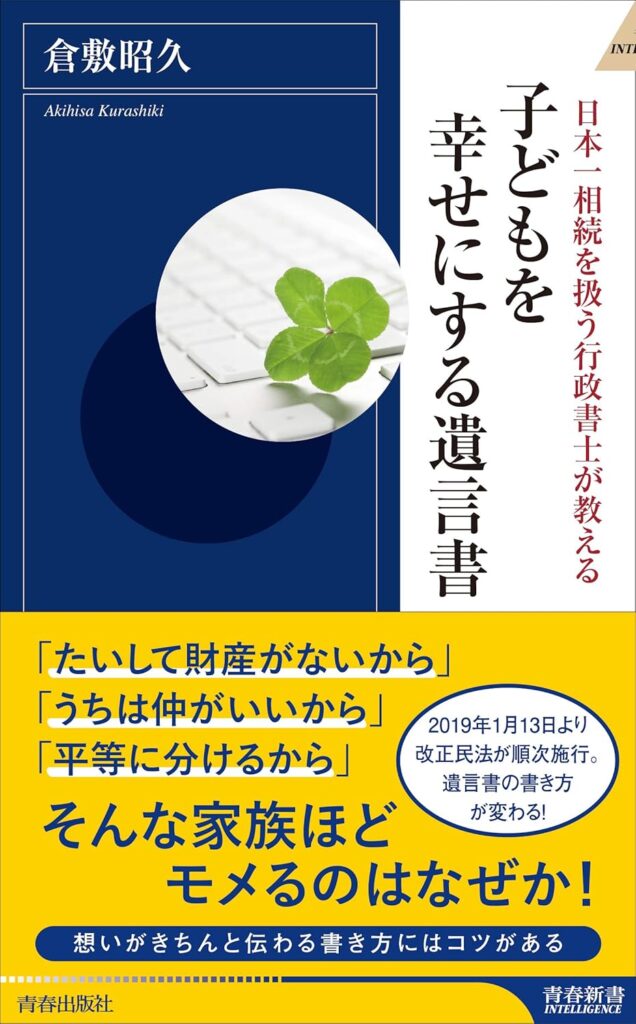
子どもを幸せにする遺言書(青春新書インテリジェンス)
著者:倉敷昭久
出版社:青春出版社
販売:https://amzn.asia/d/6tCijPD